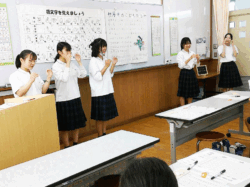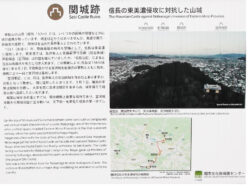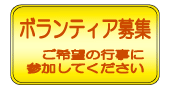第4回活動 「関有知高校生徒の皆さんと交流しよう」
2024,8,24(土)
〔12名参加、保護者1名、安全管理員3名〕
高校生のみなさんに出迎えられ、学年に応じた調理実習・小学生を飽きさせない点字・手話の学習等、用意周到な準備と個別指導のお陰で充実したひと時を過ごすことができました。
先ず、なじみある野菜に含まれる栄養クイズにより、野菜の摂取の大切さを学んでから、エプロン等を着用して調理室へ移動して、予め準備していただいた野菜を練りこんだクッキー生地を、包丁で切ったり型押しで抜いたりして形を整えて、オーブン用トレイに並べました。
低学年チームは数えたら74個ありました。高学年チームは包丁やまな板を洗って片付けることまでできました。






教室移動しトイレを済ませて、校舎探検に連れて行ってもらい、介護や保育の実習が出来る施設や園児の興味を引く掲示物を見せてもらいました。
戻ると点字の一覧表や点字を打つ器具などが用意されていて、早速、自分の名前の一字一字を高校生のみなさんに教えてもらいながら点字表で調べて書き表し、裏返して点字を打つ器具で一度練習して、ネームプレート用のシールに点字しました。
高校生のみなさんは「世界中のこどもたちが」の歌詞と手話の動作を解説してから前で向き合う人と動作をまねしやすい後ろ向きに分かれて歌いながら手話をリードしてくれました。

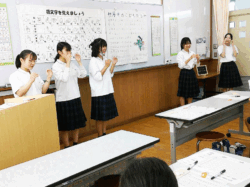


次に自分の名前の一字一字の指文字を教えてもらい、「私の名前は○○○○です。」と、自己紹介する練習をしました。
予定された活動終了後に今日の体験に関するアンケートを記入する間に、焼きあがって野菜シール付き包装の野菜クッキーが配られました。
最後に高校生のみなさんが手話で自己紹介していただきました。
集合の時から、関有知高校の廣江修校長先生が、ふれあい活動の様子を優しく見守っていただけました。



8:50 関有知高校生活デザイン科棟集合、受付、名札確認
9:00 野菜の栄養についてクイズと説明、エプロン等を着用
9:15 調理室移動、野菜クッキー作り、オーブン用トレイ
9:40 後片付け、移動、トイレ休憩
9:50 生活デザイン科棟の特別教室の見学
10:00 点字ネームプレートの作製、歌にあわせた手話
10:40 指文字を用いた自己紹介の練習、隣同士で見合う
11:00 高校生自己紹介、じゃんけんゲーム等
11:25 退出
2024,8,24(土)
下有知小学校放課後ふれあいクラブコーディネーター
松田 和彦
第3回活動 「修徳義校跡・井神社・白山神社へ行こう」
2024,07,20(土)
〔 8名参加、保護者2名、安全管理員4名 〕
朝の8時過ぎに一雨あり、集合して出発するころには日差しもありで、大変蒸し暑い中の活動となりました。
平成17(2005)年4月に廃止になった美濃町線跡を歩き、神光寺駅跡を確かめて、更に北進して元の神光寺駅があったと思われる所から東面して神光寺・白山神社に向かいました。


美濃西国二十四番霊場」の標柱があるアーチ門をくぐり、石段を上り神光寺本堂横の坂を更に上り白山神社拝殿に辿り着きました。
神社総代の山田菊雄さんと山田秀雄さんが各自に冷水を用意して出迎えていただき、一息ついてから二基の御神輿を見たり持ち上げさせてもらったりしました。
以前は、神輿を担いで神社を周回したり、5月に御輿野(おこしや:現在の中組集会所周辺にあった原っぱ)まで渡御したりする神事があったそうです。
拝殿の格天井に気づいて質問する5年生の姿もありました。


神光寺境内の旧井神社、仁王像、「今宮山」扁額を見て、山門前の石仏を数えてから、井神社・組合事務所へ行きました。
平田益夫さんから曽代用水の紹介ビデオを見せてもらい、次に曽代用水の水量を調製する遠隔操作盤の説明をしてもらいました。
長良川の増水時や大雨で降った雨水が大量に用水に流れ込んだときの対応の困難さが子ども達にも伝わりました。


外に出て「水車同業者」寄進の石灯籠や「井水、井川?」の意匠がある旧社務所の鬼瓦や曽代用水顕彰碑を見て歴史に触れた後、用水に流れてくる草木やごみを揚げる機械を見て、ごみの量や大きさに驚かされました。
最後に洞泉寺へ行き、150年前の学校の様子を明治期の井神社祭礼の写真を参考に想像してみました。

8:50 中組集会所集合、受付、保険掛金回収、名札確認
9:00 旧神光寺駅跡、神光寺標柱、アーチについて説明
9:15 白山神社拝殿、水分補給、御神輿見学
9:50 神光寺境内井神社跡、山門、石仏群の見学
10:10 曽代用水土地改良区組合事務所・井神社見学
10:45 洞泉寺、修徳義校跡を巡る
11:10 秋葉神社、唐栗神社を巡る
11:30 中組集会所到着
2024,7,20(土)
下有知小学校放課後ふれあいクラブコーディネーター
松田 和彦
| 第2回活動 「木材片を利用して工作を楽しもう」2024,6,15(土) |
木工作の材料は、高橋正次さん達が山王山の登山道整備で伐採した枝や高橋さんが長野県などに出かけられた折に入手された木材などを用いて、かなり前から入念に数多く準備していただきました。
時間内に活動を終えるため、見本となるトンボやうさぎなど小動物を模した作品も数多く準備され、迷わずに木工作品がイメージできるようにしていただきました。
それに、ドリルの穴あけや木片の切断等、児童には難しい作業もあるということで、登山道整備仲間の鳥本哲夫さんにも応援に来ていただきました。






用意していただいた見本例とそれらの組み合わせるパーツの木片類とを見比べ、材料を手にとって選ぶことから始まりました。
いろいろな大きさに裁断して磨いたり穴を開けたりして加工した木片を、ボンドで接着して見本のトンボやうさぎなどからイメージした作品に上げる作業は順調に進み、次から次へと作品の材料を選んで工作することを集中して、どの子も3回以上繰り返すことができました。






見本の作品を手がかりに、選んだ材料の大小や数の差や参加者個々の豊かな発想やで、個性溢れる作品ができました。予定通していた休憩時刻10:00より30分過ぎて、休憩と友達の作品を見る時間をとりました。
自分の思い描いたように木の枝や年輪の美しい木片などを組み合わせるために、ドリルの穴あけ・木片の切断・グルーガンでの接着などの手助けの依頼や受け答えから、地域の方と自然に交流することができました。




家でも今日の体験を活かして、作品づくりができるよう材料を持ち帰ることができることと仕上げにオイルを含ませた布で磨き上げるアドバイスがあった後、10月開催の下有知の文化祭に出品できるように保管することを参加者、保護者にお願いしつつ散会しました。文化祭での作品展示が楽しみです。




| 8:30 講師や安全管理員の皆さんで準備
8:50 受付、保険掛金回収、名札確認
9:00 挨拶、講師紹介、工作について説明
9:10 作りたい作品の材料を選び取る ※作品づくり
10:30 休憩、友達の作品を見て回る ~ 10:40 ※
11:10 作りかけの作品の仕上げ |
11:15 片付け、整理整頓 11:30 解散
2024,6,15(土)
下有知小学校放課後ふれあいクラブコーディネーター
松田 和彦
| 第1回活動 「軽スポーツ三種目(玉入れなど)で遊ぼう」
〔 10名参加、保護者6名、安全管理員5名 〕‘24,5,19(日) |
開会式では、ふれあいクラブ実行委員会会長の横山伸治さんから歓迎と期待を込めたあいさつをいただき、指導者代表の纐纈明さんから指導者の紹介と説明を受けました。
次いで、9時から11時半まで、児童10名と保護者6名と安全管理員4名等で9名ずつの3チームに分かれて、Aチームはサスケ玉入れ、Bチームはシャッフルボード、Cチームはラダーゲッターを始めに軽スポーツ三種目を順に体験しました。


ゲームを始める前には、各種目の指導者から十分な指導を受け練習をしました。
サスケ玉入れは高さが上がる3つの籠にチーム全員で玉を全部入れてしまうタイムを計りました。
シャッフルボードは一人一人が細長い棒で4枚のディスクを順にコートの得点の的をねらって押し出して得点を競いました。
ラダーゲッターは両端にボールがある3本の綱をラダー(はしご)に投げて引っ掛ける位置で得点を競いました。【↓玉入れ、シャッフル、ラダーの順】




種目ごとに投げ方や押し方をあれこれ調整して、あきらめず何度も何度も繰り返す姿が見られたり声援や拍手が聞こえたりと、指導者とかかわりながら、指先から足腰の全身、頭脳を使って、どの種目にも熱心にチャレンジできました。
| Aチーム |
5分25秒 |
250点 |
92点 |
| Bチーム |
3分22秒 |
192点 |
46点 |
| Cチーム |
3分28秒 |
183点 |
83点 |


後片付けやモップがけまで、委員の方から指導いただいて、楽しく充実した一時を過ごすことができました。
同時に下有知のいろいろな組織に支えられている「ふれあい活動」のスタートを切ることができました。
| 8:00 スポーツ推進委員、体育委員の皆さんで準備
8:50 受付、保険掛金回収、名札確認
9:00 開会式、会長挨拶、説明、推進員・委員等紹介
9:15 軽スポーツ三種目に挑戦 9:50 休憩
10:05 チーム毎に、残りの種目に挑戦
11:05 自由に種目を選んで挑戦 |
11:15 成績発表、片付け、モップがけ 11:30 解散
2024,5,19(日)
下有知小学校放課後ふれあいクラブコーディネーター
松田 和彦
第11回 「安全に気をつけて配水池のある水道山・安桜山に登ろう」
〔7名参加、保護者5名、安全管理員3名〕 2024,2,10(土)
先月は安桜山登山を天候不良のため見送りましたが、今月の三連休初日は好天に恵まれました。参加児童7名と5名の保護者で実施しました。
わかくさプラザロビーに予定通りに集合し、市役所南、西本郷通4交差点、旧学校給食センター横を通り、山裏から水道山に登りました。水道施設であるため、フェンス越しに小瀬水源地からポンプアップされる水道水を溜める大きな貯水槽を確認しました。近くにカモシカを生け捕りにするための罠が設置されていて驚かされました。






善光寺本堂横を通り、大梵鐘の在る所に移動して、県下最大の鐘を希望者がつきました。明治43(1910)年に日露戦争戦没者慰霊のために設置された四国八十八ヶ所巡りを一番から見て、21,23番の下有知が刻まれている石仏を確かめてから展望台まで一気に登りました。展望台から長良川や学校の校舎などの施設を確かめたり、北側の下有知と南側の関市街を比べたりしました。展望台から下りて、標高152mの山頂(関城本丸跡)で御嶽神社傍らの三角点を確かめたり、「當所○屋△△兵衛」など彫られた石柱の文字を読んでみたりして、歴史的に重要な地点であることを実感しました。サイレン塔での休憩時、好ましい活動を尋ね挙手してもらったところ、身体を動かすゲームと工作とが多く、野外活動は少数派でした。






八木和弘さん・松田邦子さん両名の指導の下、体力づくりと視点を変えて下有知を見ることができました。
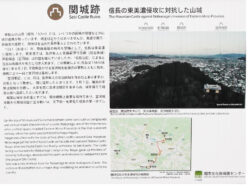

8:30 打ち合わせ、受付準備
8:40 受付開始、講師紹介、出発
9:10 水道山配水池
9:25 善光寺本堂 トイレ休憩
9:35 鐘楼 大梵鐘 鐘つき(希望者)
四国八十八ヶ所巡り(一番~四十八番)
10:00 安桜山展望台 下有知の主な建物、施設確認
10:20 山頂御嶽神社境内、三角点、記名石柱確認
10:35 大手道下山(九~六合目道標)
10:45 サイレン塔 休憩(活動内容の好みを挙手確認)
11:00 安桜山公園、トイレ、わかくさトンネル
11:25 わかくさプラザ、挨拶、解散
2024,2,10(土)
下有知小学校放課後ふれあいクラブコーディネーター
松田 和彦